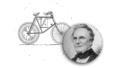折りたたみ電動バイク人気おすすめランキングTOP10
ここでは、機能性やデザイン、コストパフォーマンスなどを総合的に判断し、今人気のおすすめ折りたたみ電動バイクをランキング形式でご紹介します。あなたのライフスタイルに合う一台が、きっと見つかるはずです。
10位:RICHBIT CITY

特定小型原付モデルとして、手軽に乗り始められる一台です。スタイリッシュなデザインが特徴で、街乗りに映えます。16インチのタイヤで安定感もあり、快適な走行が楽しめます。バッテリーが取り外し可能なため、室内での充電も簡単です。手軽さとデザイン性を両立させたい人におすすめです。
9位:COSWHEEL MIRAI S

自転車モード、ハイブリッドモード、バイクモードの3つの顔を持つ個性的な一台です。その日の気分やバッテリー残量に合わせて、ペダルを漕いだり、完全に電動で走行したりと、乗り方を選べます。太いタイヤがもたらす安定感と、力強い走りが魅力。アウトドアなど、アクティブなシーンでも活躍してくれます。
8位:ブレイズ EVスクーター

立ち乗りも座り乗りもできる、ユニークな電動スクーターです。折りたたむと非常にコンパクトになり、車に積んで出かけるのにも便利。ちょっとした移動を手軽に楽しみたい、そんなニーズに応えてくれます。個性的なスタイルで、注目を集めること間違いなしの一台です。
7位:Acalie SWIFT HORSE K2

タイヤサイズまで折りたためるという、驚きのコンパクトさを実現した特定小型原付モデルです。折りたたんだ状態でスーツケースのように引いて運べるため、持ち運びの負担が少ないのが特徴。都市部での移動や、公共交通機関との連携を考えている人に最適です。
6位:glafit NFR-01 Pro

自転車とバイクの機能を融合させた「ハイブリッドバイク」という新しいジャンルを切り開いたモデルです。ペダルを漕ぐことも、スロットルを回してバイクとして走ることも可能。高品質なパーツが使われており、信頼性が高いのも魅力です。長距離の移動も快適にこなせる実力派です。
5位:ブレイズ スマートEV

100%電気で動く、まさに「小さなバイク」です。折りたたむと驚くほどコンパクトになり、車のトランクにもすっぽり収まります。家庭用コンセントで約3.5時間でフル充電でき、約30kmの走行が可能です。豊富なカラーバリエーションも魅力で、自分らしい一台を選べます。毎日の足として、また休日の相棒として、幅広く活躍してくれます。
4位:YADEA TROOPER-01

電動バイクの世界的な大手メーカーYADEAが手掛けるモデルです。極太のタイヤが特徴的で、安定した力強い走りを提供します。デザイン性も高く、所有する喜びを感じさせてくれます。品質とパワフルな走りを求める人におすすめの一台です。バッテリーの持ちも良く、長めの距離を走りたい人にも対応できます。
3位:glafit NFR-01 Lite

glafitのハイブリッドバイクを、特定小型原付として乗れるようにしたモデルです。免許不要で、自転車のようにペダルを漕いで走ることもできます。最高速度は20km/hに制御されていますが、その手軽さは大きな魅力です。信頼性の高いブランドの製品に、安心して乗りたいという人にぴったりです。
2位:COSWHEEL SMARTEV

特定小型原付モデルでありながら、原付一種への切り替えも可能な二刀流モデルです。力強いモーターと大容量バッテリーを搭載し、坂道でもスムーズに走行できます。前後サスペンションが装備されており、乗り心地も非常に快適。性能と使い勝手のバランスが良く、多くの人におすすめできるモデルです。
1位:glafit X-SCOOTER LOM

栄えある1位は、glafitが開発した特定小型原付の電動キックボード「LOM」です。安定性の高い二輪のスクータータイプで、誰でも安心して乗ることができます。折りたたみも簡単で、デザインも洗練されています。安全性と使いやすさ、そしてデザイン性を高いレベルで融合させた、まさに次世代の乗り物です。日常の移動を、もっとスマートで楽しいものに変えてくれるでしょう。
今、折りたたみ電動バイクが人気の理由とは?
最近、街中でスタイリッシュな電動バイクを見かける機会が増えていませんか。特に、折りたたみ可能な電動バイクが大きな注目を集めています。その理由は、私たちの生活スタイルにぴったり合う、たくさんの魅力が詰まっているからです。
一番の魅力は、その手軽さにあります。電車やバスのような公共交通機関と組み合わせることで、移動がもっと自由になります。例えば、自宅から最寄り駅まで電動バイクで行き、折りたたんで電車に乗り込む。そして、目的地の駅からまたバイクで移動する、といった使い方ができるのです。車で行くほどではないけれど、歩くには少し遠い、そんな距離の移動に最適です。行動範囲がぐっと広がり、新しい発見があるかもしれません。
経済的であることも、人気の理由の一つです。ガソリン価格の変動に一喜一憂することなく、自宅のコンセントで手軽に充電できます。電気代はガソリン代に比べて非常に安く、毎日の通勤や通学にかかるコストを大幅に抑えることが可能です。環境に優しいという点も、現代の価値観に合っています。排出ガスを出さないため、クリーンな移動手段として選ばれています。
そして、保管場所に困らないコンパクトさも見逃せません。一般的なバイクのように広い駐車スペースを必要とせず、折りたたんで玄関やベランダ、物置などに収納できます。都市部のマンションなど、限られたスペースで暮らす人にとって、これは非常に大きなメリットです。
後悔しない!折りたたみ電動バイクの選び方5つのポイント
たくさんの種類がある折りたたみ電動バイクの中から、自分に合った一台を見つけるのは大変かもしれません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえておけば、きっと満足のいく選択ができます。ここでは、購入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないための、5つの選び方のポイントを解説します。
1. 「公道走行」できるかどうかを確認する
まず最も大切なのが、公道を走るかどうかです。電動バイクには、公道を走行できるモデルと、公園や私有地での利用に限定されたモデルがあります。通勤や街乗りに使いたいなら、必ず公道走行可能なモデルを選ばなくてはなりません。公道を走るためには、ウインカーやブレーキランプ、ミラーといった保安部品(※1)が正しく装備されている必要があります。購入を検討しているバイクが、道路運送車両法に定められた基準を満たしているか、しっかりと確認しましょう。
2. 免許は必要?「車両区分」をチェック
公道走行可能なモデルには、主に「原付一種」と「特定小型原動機付自転車(※2)」の二つの区分があります。原付一種は、従来の50ccバイクと同じ扱いで、運転には原付免許以上が必要です。一方、特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で運転できます。ただし、交通ルールは守らなくてはなりません。どちらの区分に該当するかで、必要な免許やヘルメット着用の義務などが変わってくるため、自分の状況に合った区分を選ぶことが重要です。
3. どのくらい走れる?「航続距離」
一度のフル充電でどれくらいの距離を走れるかを示す「航続距離」は、使い勝手に直結する重要なスペックです。毎日の通勤で使うなら、往復の距離よりも余裕のある航続距離を持つモデルを選ぶと安心です。例えば、片道10kmの距離なら、バッテリーの劣化なども考慮して30km以上の航続距離があると良いでしょう。短い距離の移動がメインなら、それほど長い航続距離は必要ないかもしれません。自分の主な使い方を想像して、最適な航続距離を見極めましょう。
4. 持ち運べる?「車体の重さ」
折りたたんで持ち運ぶシーンが多いなら、車体の重さは無視できません。とくに、電車に乗せたり、階段を使って部屋まで運んだりすることを考えると、軽いに越したことはありません。一般的に20kgを超えると、持ち運びは少し力が必要になります。一方で、15kgを下回るような軽量モデルも存在します。デザインやバッテリー容量とのバランスも考えながら、自分が無理なく扱える重さのモデルを選びましょう。
5. 乗り心地を左右する「タイヤのサイズ」
意外と見落としがちですが、タイヤのサイズは乗り心地や安定性に大きく影響します。タイヤが小さいと、小回りが利いてコンパクトに収納できるメリットがあります。しかし、段差や路面の凹凸からの衝撃を受けやすくなります。逆にタイヤが大きいと、安定性が増し、快適な乗り心地になりますが、その分、車体は大きく重くなる傾向があります。走行する道の状況や、乗り心地の好みに合わせて、適切なタイヤサイズを選んでください。
※1 保安部品:安全に公道を走行するために法律で定められた装置のこと。ライト、ウインカー、ブレーキ、ミラー、警音器(クラクション)などが含まれる。
※2 特定小型原動機付自転車:2023年7月の法改正で新設された車両区分。最高速度20km/h以下などの基準を満たし、16歳以上なら免許不要で運転できる。
【特定小型原付】免許不要で乗れる!注目の折りたたみ電動バイク
2023年7月1日から始まった「特定小型原動機付自転車」という新しい制度は、私たちの移動をより手軽なものに変えました。これは、一定の基準を満たす電動キックボードなどを、16歳以上であれば運転免許なしで利用できるという画期的なルールです。
この特定小型原付に分類される折りたたみ電動バイクは、まさに現代の移動ニーズにマッチした乗り物です。ヘルメットの着用は努力義務とされていますが、安全のためには着用を強くおすすめします。最高速度は時速20kmに制限されており、スピードが出すぎない設計になっています。
さらに、時速6km以下で走行する「特例モード」に切り替えることで、一部の歩道を走行することも可能です。このモード中は、車体の最高速度表示灯が緑色に点滅し、周りに歩道を走行中であることを示します。これにより、車道を走るのが怖いと感じる場所でも、安心して移動を続けられます。
ただし、免許が不要だからといって、交通ルールを守らなくていいわけではありません。信号を守る、一時停止をするといった基本的なルールはもちろん、飲酒運転は絶対に禁止です。また、自賠責保険への加入とナンバープレートの取得は必須となります。手軽に乗れるからこそ、一人ひとりが交通社会の一員であるという意識を持って、安全に利用することが大切です。
人気メーカーの特徴を比較!あなたに合うのはどれ?
折りたたみ電動バイクを選ぶとき、どのメーカーの製品にするか迷うことも多いでしょう。ここでは、特に人気の高い代表的なメーカーの特徴を紹介します。それぞれのメーカーが持つ哲学や強みを知ることで、あなたにぴったりの一台が見つけやすくなります。
glafit(グラフィット)
和歌山県に本社を置く、日本のモビリティベンチャーです。「自転車+バイク」というコンセプトのハイブリッドバイクを世に送り出し、大きな話題となりました。製品の品質や安全性へのこだわりが強く、ユーザーからの信頼も厚いメーカーです。法改正にもいち早く対応し、特定小型原付モデルも積極的に展開しています。日本の交通事情をよく理解した製品づくりが魅力で、安心して長く使える一台を求める人におすすめです。
COSWHEEL(コスウエル)
パワフルでデザイン性の高い電動バイクを多くラインナップしているメーカーです。太いタイヤと力強いモーターを搭載したモデルが特徴で、安定感のある走りを実現しています。1台で特定小型原付と原付一種を切り替えられるユニークなモデルなど、利用者のニーズに応える多彩な製品を開発しています。性能や走りの楽しさを重視する人に、特に支持されています。
BLAZE(ブレイズ)
愛知県に本社を置く、ユニークな電動モビリティを企画・販売している会社です。折りたたむと非常にコンパクトになる「スマートEV」や、立ち乗りもできる「EVスクーター」など、遊び心あふれる製品が揃っています。デザインやコンセプトが個性的で、他の人とは違う一台に乗りたいという方にぴったりです。コンパクトさと楽しさを追求するなら、ぜひチェックしたいメーカーです。
YADEA(ヤディア)
世界中で大きなシェアを誇る、電動バイクのグローバルメーカーです。長年培ってきた高い技術力と生産能力を背景に、高品質で信頼性の高い製品を提供しています。デザインも洗練されており、グローバル基準の性能とスタイルを求める人から高い評価を得ています。世界で認められた品質と走りを体感したいなら、YADEAのモデルは有力な選択肢になるでしょう。
折りたたみ電動バイクのメリット・デメリットを徹底解説
新しい移動手段として魅力的な折りたたみ電動バイクですが、購入する前には良い点だけでなく、注意すべき点も理解しておくことが大切です。ここでは、メリットとデメリットの両方を詳しく見ていきましょう。
メリット
圧倒的な手軽さと利便性
最大のメリットは、その手軽さです。折りたたんで車に積んだり、電車に持ち込んだりできるため、行動範囲が格段に広がります。「ラストワンマイル」と呼ばれる、駅から目的地までの最後の少しの距離を快適に移動できるのは、大きな魅力です。
経済的で環境に優しい
ガソリンを使わず、家庭用コンセントで充電できるため、燃料費を大幅に節約できます。日々の維持費が安いのは、長く使い続ける上で嬉しいポイントです。また、走行中に排出ガスを一切出さないため、環境への負荷が少ないクリーンな乗り物です。
保管場所に困らない
一般的なバイクと違い、専用の駐車スペースを確保する必要がありません。折りたたんで玄関先や自宅の中に保管できるため、盗難のリスクを減らすこともできます。都市部の集合住宅などでも、保管場所に悩むことが少ないでしょう。
デメリット
航続距離に限りがある
バッテリーで動くため、一度の充電で走れる距離には限界があります。長距離のツーリングなどには向いていません。外出先でバッテリーが切れてしまうと、ただの重い乗り物になってしまうため、事前の充電と計画的な利用が不可欠です。
パワーと安定性の限界
コンパクトで軽量な設計のため、急な上り坂ではパワー不足を感じることがあります。また、タイヤが小さいモデルが多いため、大きなバイクに比べると段差などでの安定性は劣ります。路面の状況には、より注意を払って運転する必要があります。
天候の影響を受けやすい
屋根がないため、雨や雪、強風などの悪天候時には利用が難しくなります。雨の日は、電気系統の故障のリスクや、路面が滑りやすくなる危険性も高まります。天候に左右される乗り物であることは、あらかじめ理解しておく必要があります。
知っておきたい!公道走行のルールと注意点
折りたたみ電動バイクで公道を走ることは、とても便利で楽しい体験です。しかし、安全に楽しむためには、守るべき交通ルールを正しく理解しておく必要があります。ここでは、特に重要なポイントを解説します。
自賠責保険とナンバープレートは必須
公道を走行するすべての電動バイクは、自動車やバイクと同じように「自賠責保険(※3)」への加入が法律で義務付けられています。これは、万が一の交通事故で相手にケガをさせてしまった場合の補償をするための保険です。また、お住まいの市区町村の役所で手続きを行い、ナンバープレートを取得して車体に取り付ける必要があります。これらがない状態で公道を走ると、厳しい罰則の対象となります。
車道走行が基本
電動バイクは、車両の仲間です。したがって、歩道と車道の区別がある道路では、原則として車道の左側を走行しなければなりません。自転車のように気軽に歩道を走ることはできませんので、注意が必要です。ただし、先述した「特定小型原付」の特例モードであれば、標識で許可された一部の歩道を徐行して通行できます。
ヘルメットの着用について
原付一種に分類されるモデルを運転する場合は、オートバイと同様にヘルメットの着用が義務付けられています。着用していないと、交通違反となります。一方、特定小型原付の場合は、ヘルメットの着用は「努力義務」とされています。しかし、万が一の事故の際に頭部を守ることは、命を守る上で非常に重要です。自分の安全のために、必ずヘルメットを着用するようにしましょう。
飲酒運転は絶対にしない
手軽に乗れるからといって、お酒を飲んだ後に運転することは、絶対に許されません。飲酒運転は、自分だけでなく他人の命を危険にさらす、極めて悪質な行為です。電動バイクも法律上は車両であり、飲酒運転には非常に厳しい罰則が科せられます。ルールを守り、安全な利用を心がけましょう。
※3 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険):交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補うことにより、基本的な対人賠償を確保することを目的とした保険。
バッテリーの寿命とメンテナンス方法は?
電動バイクの心臓部とも言えるのがバッテリーです。快適に長く乗り続けるためには、バッテリーの特性を理解し、適切なメンテナンスを行うことが大切です。ここでは、バッテリーの寿命や日頃のケアについて解説します。
バッテリーの寿命
電動バイクに使われているリチウムイオンバッテリーは、スマートフォンなどと同じように、充電を繰り返すことで少しずつ劣化していきます。一般的には、充電回数にして300回から500回程度が寿命の目安とされています。使い方や保管状況によって変わりますが、毎日充電して乗るような使い方であれば、2年から3年ほどで性能の低下を感じ始めるかもしれません。性能が落ちると、満充電しても走れる距離が短くなっていきます。多くのモデルではバッテリーを交換することができるので、航続距離が著しく短くなったら交換を検討しましょう。
長持ちさせるためのポイント
バッテリーを長持ちさせるためには、いくつかのコツがあります。まず、「過充電」と「過放電」を避けることです。充電が100%になっても長時間コンセントに繋ぎっぱなしにしたり、バッテリー残量が0%のまま長期間放置したりすると、バッテリーに大きな負担がかかります。保管する際は、残量を50%程度に保っておくのが理想的です。また、バッテリーは極端な高温や低温にも弱い性質があります。真夏の直射日光が当たる場所や、冬の氷点下になるような場所での保管は避けるようにしましょう。
日頃のメンテナンス
電動バイク自体のメンテナンスも重要です。特に、タイヤの空気圧は定期的にチェックしましょう。空気圧が低いと、走行抵抗が増えてバッテリーの消耗が早くなるだけでなく、パンクの原因にもなります。ブレーキの効き具合も、乗る前に必ず確認する習慣をつけたいものです。また、雨天時に走行した後は、水分をしっかりと拭き取り、チェーンなどの金属部分が錆びないようにケアすることも大切です。日頃のちょっとした気遣いが、愛車を長く良い状態に保つ秘訣です。
折りたたみ電動バイクに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、折りたたみ電動バイクの購入を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問点を解消して、安心して新しいモビリティライフを始めましょう。
Q. 雨の日に乗っても大丈夫ですか?
A. 多くのモデルは、ある程度の防水性能を備えており、小雨程度であれば走行可能な場合が多いです。しかし、電動バイクは電気で動く乗り物なので、大雨の中での走行や水たまりに勢いよく入ることは避けるべきです。感電や故障の原因になる可能性があります。また、雨の日は路面が滑りやすく、視界も悪くなるため、運転には普段以上の注意が必要です。安全のため、なるべく雨天時の使用は控えることをおすすめします。
Q. 坂道を登ることはできますか?
A. モデルのモーター出力や乗る人の体重によって異なりますが、緩やかな坂道であれば問題なく登れるモデルがほとんどです。しかし、急な上り坂ではスピードが落ちたり、登るのが難しくなったりすることもあります。坂道の多い地域で利用する場合は、モーターの出力(W数)が大きい、パワフルなモデルを選ぶと良いでしょう。可能であれば、購入前に試乗して登坂性能を確認できると安心です。
Q. どこで購入できますか?
A. インターネットの公式オンラインストアや、大手通販サイトで購入できます。また、家電量販店や自転車専門店、バイク販売店など、実店舗で取り扱っている場合もあります。実店舗であれば、実際に車体を見たり、試乗させてもらえたりするメリットがあります。購入後のメンテナンスや修理の相談もしやすいため、近くに取り扱い店舗があるか調べてみるのも良いでしょう。
Q. 任意保険には入ったほうが良いですか?
A. 加入が義務付けられている自賠責保険は、相手方の身体への損害(ケガや死亡)しか補償されません。相手の物(車やガードレールなど)を壊してしまった場合や、自分自身のケガについては補償の対象外です。万が一の高額な賠償請求に備えるためにも、対物賠償や人身傷害をカバーする任意保険への加入を強くおすすめします。自転車保険などに付帯できる個人賠償責任特約が使える場合もあるので、ご自身の保険状況を確認してみましょう。
まとめ:あなたにぴったりの一台で、新しい移動体験を
折りたたみ電動バイクは、私たちの移動をより自由に、そしてスマートにしてくれる可能性を秘めた乗り物です。電車や車と組み合わせることで行動範囲は大きく広がり、ガソリンを使わないことで経済的かつ環境にも貢献できます。保管場所に困らないコンパクトさも、現代のライフスタイルにぴったりです。
この記事では、後悔しないための選び方のポイントから、人気のモデル、知っておくべきルールまで、幅広く解説してきました。大切なのは、自分の生活の中で「どのように使いたいか」を具体的にイメージすることです。毎日の通勤で使うのか、休日のちょっとしたお出かけに使うのか。それによって、必要な航続距離や重視すべき機能も変わってきます。
特定小型原付という新しい制度により、免許不要で乗れるモデルも増え、そのハードルは以前よりもずっと低くなりました。しかし、手軽だからこそ、交通ルールを守り、安全への意識を常に持つことが何よりも重要です。ヘルメットを着用し、保険に加入し、周りに配慮した運転を心がけましょう。
たくさんの選択肢の中から、デザイン、性能、使い勝手などをじっくり比較検討し、あなたにとって最高のパートナーとなる一台を見つけてください。そして、折りたたみ電動バイクと共に、新しい景色を見に出かけましょう。