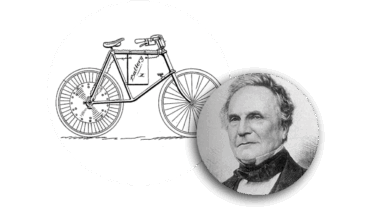電動バイクとは?基本的な仕組みを解説
電動バイクとは、その名の通り「電気」をエネルギーにして走るバイクを指します。ガソリンで動くバイクがエンジンを搭載しているのに対し、電動バイクは電気で動くモーターを積んでいます。とてもシンプルな仕組みです。
家庭にあるコンセントなどからバッテリーに電気を蓄えます。その蓄えた電気を使い、モーターを回転させてタイヤを動かすのです。ちょうど、スマートフォンの充電と似ています。家に帰ったら充電し、次の日に使うという感覚です。
電動バイクの心臓部は、主に3つのパーツで構成されています。一つ目は電気を蓄える「バッテリー」です。これがガソリンバイクでいうガソリンタンクの役割を果たします。二つ目は、電気の力でタイヤを動かす「モーター」です。これがエンジンにあたります。そして三つ目が、モーターに送る電気の量を調整する「コントローラー」です。これがバイクの動きを制御する頭脳部分と言えるでしょう。これらの部品が連携することで、静かで滑らかな走行が実現します。
電動バイクとガソリンバイクの決定的な違い
電動バイクとガソリンバイクは、見た目が似ていても中身は全く異なります。最大の違いは、やはり動力源です。ガソリンを燃やして動くか、電気で動くかという点です。
この動力源の違いが、様々な特徴の違いを生み出します。例えば「音」です。ガソリンバイクはエンジンから特有の排気音や振動が発生します。一方、電動バイクはモーターで動くため、走行音が非常に静かです。「ウィーン」というモーターの作動音がするだけで、ほとんど無音に近い感覚で走ります。
加速感も大きく異なります。電動バイクは、アクセルをひねると瞬時に最大級の力を発揮する特性があります。信号待ちからのスタートなどで、驚くほどスムーズで力強い加速を体験できるでしょう。これは「トルク」(注1)と呼ばれる、タイヤを回転させる力の出方がガソリンエンジンと根本的に違うためです。
また、メンテナンスの手間にも差があります。ガソリンバイクには定期的なエンジンオイルの交換や、スパークプラグなどの消耗品の点検が必要です。しかし電動バイクは、これらの部品が存在しないため、メンテナンスの手間や費用を大幅に抑えることができます。
注1:トルク…物体を回転させる力の強さのこと。電動バイクは、回転し始めから大きなトルクを発生させることができるため、発進がスムーズです。
知っておきたい!電動バイクの3つの大きなメリット
電動バイクには、ガソリンバイクにはない魅力的なメリットがたくさんあります。その中でも特に大きな3つのメリットを紹介します。
一つ目は「環境への優しさ」です。電動バイクは走行中に排出ガスを一切出しません。地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)や、大気汚染につながる有害な物質をまき散らすことがないのです。都市部の空気をきれいに保つことにも貢献できる、クリーンな乗り物です。
二つ目は「経済的な負担の軽さ」です。日々の燃料代を考えてみましょう。ガソリン価格は変動が激しいですが、電気料金は比較的安定しています。一般的に、同じ距離を走った場合の電気代はガソリン代よりもかなり安く済みます。さらに、前述の通りオイル交換などの維持費もかかりにくいため、長く乗るほど経済的なメリットが大きくなります。
三つ目は「静かで快適な乗り心地」です。走行音が非常に静かなため、早朝や深夜の住宅街でも周囲に気兼ねなく移動できます。また、エンジン特有の不快な振動がほとんどありません。これにより、長時間の運転でも疲れにくく、快適なライディングを楽しむことができます。ライダー自身が周囲の環境音を聞き取りやすいという、安全面での利点も挙げられます。
購入前に要確認!電動バイクのデメリットとは?
多くのメリットがある電動バイクですが、もちろん弱点も存在します。購入してから後悔しないように、デメリットもしっかりと理解しておくことが大切です。
最も大きな課題は「航続距離」の問題です。航続距離とは、一度の充電で走れる距離のことです。ガソリンバイクが一回の給油で数百キロ走れるのに対し、電動バイクはまだその距離に及ばないモデルが多いのが現状です。特に長距離のツーリングなどを考えている場合は、航続距離が自分の使い方に合っているか慎重に確認する必要があります。
次に「充電時間」が挙げられます。ガソリンの給油が数分で終わるのに対し、電動バイクの充電は数時間かかるのが一般的です。自宅にいる夜間に充電するスタイルが基本となるため、外出先でバッテリーが切れてしまうと、簡単には回復できません。充電インフラ(注2)もガソリンスタンドほど普及していないため、事前の計画が重要になります。
そして「バッテリーの寿命と交換費用」も忘れてはいけません。スマートフォンと同じように、電動バイクのバッテリーも充放電を繰り返すうちに少しずつ劣化していきます。性能が落ちてきたら交換が必要になりますが、このバッテリーが非常に高価な部品なのです。将来的に大きな出費が発生する可能性も考慮しておきましょう。
注2:インフラ…産業や生活の基盤となる施設や設備のこと。ここでは充電スタンドやコンセント設備などを指します。
電動バイクにはどんな種類があるの?
電動バイクは、モーターの定格出力によって法律上の区分が分けられています。これはガソリンバイクの排気量による区分と同じような考え方です。
まず「原付一種」に分類されるモデルがあります。これは定格出力が0.6kW以下の電動バイクです。ガソリンバイクでいう50cc以下のクラスにあたり、手軽に乗れる入門モデルとして人気があります。
次に「原付二種」です。定格出力が0.6kWを超え1.0kW以下のものがこのクラスに該当します。ガソリンバイクの51ccから125ccのクラスに相当します。二人乗りができたり、法定速度が時速60kmになったりと、原付一種に比べて利便性が高いため、通勤や通学で使う人に選ばれています。
さらにパワフルな「軽二輪」クラスもあります。定格出力が1.0kWを超えるもので、ガソリンバイクの126ccから250ccに相当します。このクラスになると、高速道路の走行も可能になり、行動範囲が一気に広がります。
それ以上のパワーを持つ「小型二輪」クラスの電動バイクも存在します。ガソリンバイクの251cc以上に相当する、大型で高性能なモデルです。趣味として本格的なライディングを楽しみたい人向けの選択肢と言えるでしょう。
電動バイクに乗るために必要な免許は?
電動バイクに乗るために必要な免許は、先ほど紹介した車両の区分によって決まります。自分が乗りたい電動バイクがどの区分に当てはまるかを確認し、対応する免許を取得する必要があります。
定格出力0.6kW以下の「原付一種」であれば、「原付免許」または「普通自動車免許」で運転することができます。最も手軽な区分です。
0.6kWを超え1.0kW以下の「原付二種」を運転するには、「小型限定普通二輪免許(AT限定も可)」以上の二輪免許が必要です。普通自動車免許では運転できないので注意が必要です。
1.0kWを超える「軽二輪」や「小型二輪」クラスの電動バイクに乗る場合は、それぞれ「普通二輪免許(AT限定も可)」や「大型二輪免許(AT限定も可)」が必要になります。乗りたいバイクのパワーに応じて、適切な免許を選びましょう。
このように、電動バイクだからといって特別な免許が必要になるわけではありません。基本的にはガソリンバイクと同じ免許制度が適用されると覚えておくと分かりやすいです。
気になる航続距離と充電方法について
電動バイクを検討する上で、誰もが気になるのが航続距離と充電方法でしょう。これらは日々の使い勝手に直結する重要なポイントです。
航続距離は、モデルによって大きく異なります。街乗り用のコンパクトなモデルでは50km前後のものから、高性能なモデルでは200km以上走れるものまで様々です。ただし、カタログに記載されている数値は、特定の条件下での最適な値であることがほとんどです。実際の走行では、運転の仕方や坂道の有無、気温などによって距離が短くなることを想定しておく必要があります。
充電方法にはいくつかの選択肢があります。最も基本的なのは、自宅の家庭用コンセントから充電する方法です。多くのモデルは、車体に直接ケーブルを接続して充電します。この方法が最も手軽ですが、充電完了までには数時間から十数時間かかることもあります。
アパートやマンションなどでコンセントが近くにない場合に便利なのが、バッテリーを取り外せるタイプのモデルです。重いバッテリーを部屋まで運び、室内で充電することができます。この機能があるかどうかは、住環境によって非常に重要な選択基準となります。
外出先での充電には、商業施設や自治体の施設などに設置されている公共の充電スタンドを利用する方法もあります。しかし、数はまだ限られており、事前の場所の確認が欠かせません。
維持費はどれくらい?ガソリンバイクと比較
電動バイクの大きな魅力の一つが、維持費の安さです。具体的にガソリンバイクと比べてどれくらい違うのかを見てみましょう。
最も差が出るのは燃料代、つまり電気代です。仮に1ヶ月に500km走行するとします。ガソリンバイクの場合、燃費がリッター40kmでガソリン価格が170円だとすると、約2,125円かかります。一方、電動バイクの場合、電力料金にもよりますが、同じ距離を走るための電気代は数百円程度で済むことがほとんどです。この差は、乗れば乗るほど大きくなっていきます。
税金面でも有利です。毎年かかる軽自動車税は、電動バイクの場合、その区分における最低ランクの税額が適用されることが多く、ガソリンバイクよりも安く設定されています。
メンテナンス費用も大きく削減できます。ガソリンバイクで必須のエンジンオイル交換は、電動バイクには必要ありません。オイルフィルターやエアクリーナー、スパークプラグといった定期的に交換が必要な部品も存在しないのです。もちろん、タイヤやブレーキパッドなどの消耗品は電動バイクでも交換が必要ですが、エンジン周りの維持費がほぼかからないのは大きなメリットです。
これらの要素を総合すると、電動バイクは購入後のランニングコストを大幅に抑えることができる、非常にお財布に優しい乗り物だと言えます。
失敗しない!自分に合った電動バイクの選び方
数あるモデルの中から、自分にぴったりの一台を見つけるためのポイントを紹介します。後悔しないためには、自分のライフスタイルをよく考えることが重要です。
最初に考えるべきは「主な利用目的」です。毎日の通勤で使うのか、週末の買い物に使うのか、それとも趣味のツーリングに使いたいのか。目的によって必要な航続距離やパワーが大きく変わってきます。片道10kmの通勤がメインならコンパクトなモデルで十分ですが、長距離を走りたいなら大容量バッテリーを積んだモデルが必須です。
次に「充電環境」を確認しましょう。戸建てで駐車場にコンセントがあるなら、ほとんどのモデルを問題なく充電できます。しかし、集合住宅の場合は注意が必要です。駐輪場にコンセントがないなら、バッテリーを取り外して自室で充電できるモデルが現実的な選択肢となります。
「予算」ももちろん重要です。車両本体の価格だけでなく、ヘルメットや任意保険などの初期費用も考慮に入れましょう。さらに、後述する補助金制度を利用できるかどうかも、総額に大きく影響します。事前にいくらまで出せるのかを明確にしておくと、モデルを絞り込みやすくなります。
そして最後は「試乗」です。スペック表を見るだけでは分からない乗り心地や加速感を、ぜひ実際に体感してみてください。電動バイク特有の静かさやスムーズさは、一度乗ってみないと本当の魅力は分かりません。納得のいく一台を選ぶために、試乗は欠かさないようにしましょう。
国や自治体から補助金はもらえる?
電動バイクは環境に優しい乗り物として、国や自治体が購入を後押しする制度を設けています。これらを活用すれば、定価よりもずっと安く手に入れることが可能です。
代表的なのが、国の「CEV補助金」(注3)です。これはクリーンエネルギー自動車の普及を目的とした制度で、対象となる電動バイクを購入する際に、国から一定額の補助金が交付されます。対象車種や補助金額は毎年見直されるため、経済産業省や関連団体のウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。
さらに、国からの補助金とは別に、都道府県や市区町村が独自に補助金制度を設けている場合があります。お住まいの自治体が制度を実施していれば、国の補助金と併用して受け取れることもあります。これにより、購入時の負担を大幅に軽減できる可能性があるのです。
これらの補助金制度は、申請期間や予算の上限が定められていることがほとんどです。購入を検討し始めたら、まずは自分の住んでいる地域の自治体のウェブサイトをチェックしたり、販売店のスタッフに相談したりして、利用できる制度がないか調べてみることを強くお勧めします。
注3:CEV補助金…Clean Energy Vehicle(クリーンエネルギー自動車)の略。電気自動車やプラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、そして電動バイクなどの購入時に交付される補助金のことです。